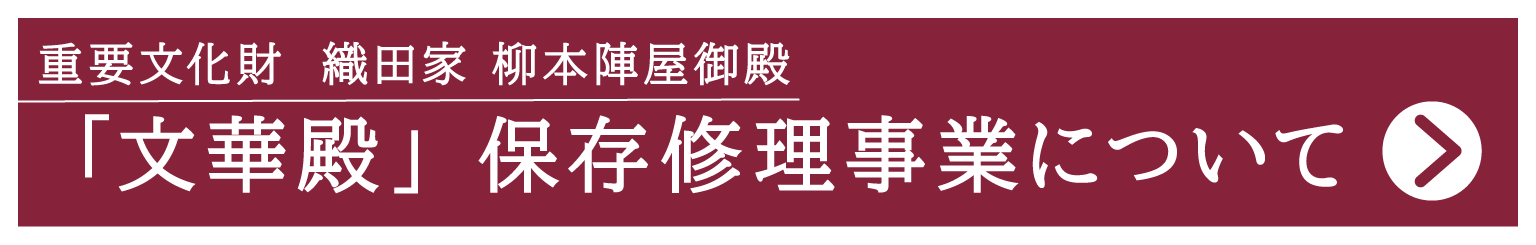お知らせ
令和4年05月24日
『春の特別参拝と重要文化財 織田家 柳本陣屋御殿「文華殿」特別公開』終了の御報告
4月22日(金)から5月8日(日)までの17日間にわたって開催いたしました『春の特別参拝と重要文化財 織田家 柳本陣屋御殿「文華殿」特別公開』が終了いたしましたので、御報告申し上げます。
今回、御崇敬の皆様と橿原神宮の御祭神との御神縁をより深めていただきたく、内拝殿での特別参拝を御案内申し上げると共に、令和2年から令和8年にかけて保存修理工事が行われている重要文化財「文華殿」の工事の裏側を御覧いただき、その建築的・文化的価値を皆様にお伝えいたしたく、特別公開を実施いたしました。

〈特別参拝にて御幣を供える参加者〉
内拝殿での特別参拝から、「文華殿」の保存修理の見学まで約1時間の行程においては、由緒などの説明と共に、神職と参加者の皆様とが直接語らう機会もあり、橿原神宮により一層親しみを持っていただけたのではないかと感じております。

〈特別参拝後の由緒説明〉

〈いよいよ、保存修理中の「文華殿」の中へ〉

〈曜日限定で行った奈良県文化財保存課様の説明〉

〈江戸城本丸大広間の屋根にも同じものが見られる千鳥破風(ちどりはふ)〉

〈下段の間にはかつて「百鳥の欄間」が存在したが、明治初期に海外に流出し、行方不明の状態〉

〈江戸後期作としては珍しい、彩色が施された丸彫りの欄間〉
開催早々には大雨や、季節外れの寒さにも見舞われましたが、5月の大型連休には天気も回復。新緑の時期に相応しい気候の中、多くの皆様に御参加をいただきました。
今後も令和8年の完成まで、保存修理の過程や特別公開の開催予定などについて、公式WEBサイト・SNSにて情報発信を行って参りますので、御注目をいただけますと幸いでございます。
令和3年09月25日
重要文化財 旧織田屋形大書院及び玄関 建造物保存修理事業に伴う工事安全祈願祭を斎行
橿原神宮では、「重要文化財 旧織田屋形大書院(おおじょいん)及び玄関(以下、文華殿)建造物保存修理事業」にあたり、令和3年9月21日(火)14時より工事安全祈願祭を斎行いたしました。
この度の保存修理事業は、文華殿の屋根瓦のズレや破損、雨漏りによる軒先の腐朽、礎石の不同沈下による床の不陸などが見られ保存に支障が出てきた為、令和2年6月より6ヶ年の継続事業として半解体修理を行う事業です。今回の工事安全祈願祭は、素屋根建設工事開始に伴い斎行いたしました。
祭典には橿原神宮をはじめ、工事関係者等の皆様にも御参列をいただき、これからの工事の安全を祈願申し上げました。



 本事業は、国や奈良県・橿原市の補助を受け、奈良県文化財保存事務所へ令和2年度から令和7年度に亘って委託し実施するものです。今後、歴史的にも貴重な遺構から様々な発見が期待されており、各工程での記者発表や特別公開を視野に入れ、重要文化財「文華殿」の新しい発見や進捗状況等を発信して参ります。
本事業は、国や奈良県・橿原市の補助を受け、奈良県文化財保存事務所へ令和2年度から令和7年度に亘って委託し実施するものです。今後、歴史的にも貴重な遺構から様々な発見が期待されており、各工程での記者発表や特別公開を視野に入れ、重要文化財「文華殿」の新しい発見や進捗状況等を発信して参ります。